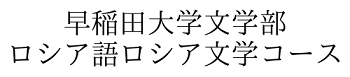2024年度提出
アンドレイ・タルコフスキー『ストーカー』論
キーラ・ムラートワ『無気力シンドローム』論──病の映画⼈間学
転形期のシクロフスキー──『第三工場』と映画論を中心に
2023年度提出
19世紀初頭ロシアのエレジーにおける瞑想の様式――ジュコフスキー「村の墓場」を中心として
ゴンチャローフ『断崖』研究――苦悩するヴェーラ
マリーナ・ツヴェターエワ「別れ」研究
2022年度提出
『カラマーゾフの兄弟』における「キリストの発見」の意義――旧約聖書ヨブ記との構造的相関に着目して
中世ロシアの聖地巡礼記録に反映された巡礼者の価値観と揺らぎ――『ルーシの地の修道院長ダニイルの聖者伝および巡礼記』を題材として
2021年度提出
イーゴリ・ホーリンの詩作における抒情的主体の変容について
ボリス・ポプラフスキイ『雪の時』読解――抒情的主体と冬の時空間
スタニスラフスキーの演技論における«переживание»とその周辺概念
2020年度提出
А.В.ルナチャルスキーの「新しい宗教」と文化政策
ベネディクト・リーフシツ『パトモス』研究
2018年度提出
ミハイル・ゾーシチェンコ『日の出前』における模倣と諷刺の問題―相反する二つの運動と不可能な欲望
アレクシエーヴィチ『セカンドハンドの時代』研究
2017年度提出
ユーリイ・オレーシャ『羨望』における語り手の戦略
マクシム・バフダーノヴィチ研究―ベラルーシ復興の詩学ー
ドストエフスキー『白痴』研究
アンドレイ・ベールイ『シンフォーニヤ』における詩学ー二重世界をめぐってー
2016年度提出
ジナイーダ・ギッピウス研究――表現としての形式
2015年度提出
前期イヴァシュキェヴィッチの散文研究
リュドミラ・ウリツカヤ短編作品群研究
2014年度提出
正書法とWebがもたらすBCSの差別化―コンピューターはクロアチア語・セルビア語・ボスニア語・モンテネグロ語を隔てるか―
ミハイル・レールモントフ『デーモン』研究―「不可解で矛盾した物語詩」の創作上の意義―
И.А. Бунин研究――その死の受容をめぐって
2013年度提出
セルゲイ・ラフマニノフのオペラ作品―各作品分析、および発展過程の研究
ソログープ『光と影』:影絵遊びとしての演劇―「変容」と「子供」のテーマ
《大審問官》における「長広舌と沈黙との対話」
イワン・ビリービンの「ビリービン様式」における装飾的な枠の消失に関して
2012年度提出
ウラジーミル・マヤコフスキーの創作における「幼児性」の詩学
エルショーフ『せむしの仔馬』―フォークロアに取材した19世紀韻文物語文学における役割―
ドストエフスキー『白痴』における身体と詩学の問題
2011年度提出
マリーナ・ツヴェターエワの長詩における夢と詩人の不在―「海より」、「部屋の試み」を中心に―
虚構の境界測定―ウラジーミル・ナボコフ『マーシェンカ』読解―
レオニード・アンドレーエフ研究-『ワシーリイ・フィヴェイスキイの一生』を中心に―
2010年度提出
アンドレイ・プラトーノフ『チェヴェングール』における身体の機能
アンドレイ・カレーリンの写真 ―演劇と絵画のあいだ―
2009年度提出
ヘンルィク・シェミラツキ研究 -受け継がれた様式と独自の技法-
メイエルホリド演劇における静的マリオネットと動的マリオネット -「人形振り」からビオメハニカへ
2008年度提出
近代民族研究の発展とともに変化してきたスラヴ民族に対する歴史認識-言語学、考古学、形質人類学、分子遺伝学の視点からロシアの起源を巡る回顧的研究
アンドレイ・ベールイ『コーチク・レターエフ』研究
チャストゥーシカの生産性を保証したものは何か
2007年度提出
『イワーノフ』論
セミョーン・フランクの思想と精神科学
『悪霊』研究 ──創作と表現の問題を中心として──
ロシアにおけるユロージヴイ(瘋癲行者) ──その歴史的背景と精神的基層──
2006年度提出
ドストエフスキーの作品におけるキリスト教救済原理とカーニバル原理 ──「死の家の記録」と「大審問官」における分析と考察──
ニコライ・フォレッゲル研究
Н. Ф. フョードロフの終末論
2005年度提出
ロシアの民衆文化における聖パラスケヴァ・ピャートニツァ信仰について ──「金曜日の人格化」の機能を中心とした民間信仰におけるその特性についての考察──
2004年度提出
グラ-スノスチ研究 ──ゴルバチョフ政権下におけるソヴィエト・メディアの活動からみる通俗的グラースノスチ観の検討およびグラースノスチの実態の考察 ──
ドストエフスキーとピカレスク小説 ──冒険小説・教養小説という要素を通して西欧通俗小説との関係の中で ──
転換期のメイエルホリド ── シンボリズム演劇の超克 ──
2003年度提出
ゲトマン・マゼーパの失墜 ――マゼーパ・テクストとしての『ポルタヴァ』
2002年度提出
マヤコフスキイ『南京虫』研究
T・トルスタヤ研究 ──言葉の突然変異を視る──
ブィリーチカにおける相補的解釈概念としての魔女とドモヴォーイ
2001年度提出
レーミゾフ「お陽さま追って」と「わたつみの海」における神話の再創造
トゥルゲーネフ『猟人日記』における風景描写 ──風景画としての『猟人日記』──
ヴェネディクト・エロフェーエフの戯曲「ワルプルギスの夜、あるいは『総督の足音』」の世界 ──悲劇とカーニバル──
ラスプーチン研究 ──『マリヤのための金』における時空間──
『白衛軍』と『巨匠とマルガリータ』 ──ブルガーコフの終末的世界観──
ヨシフ・ブロツキー『ジョン・ダンに捧げる大エレジー』 ──“ことばの遠心力”とはなにか──
アレクサンドル・ソルジェニーツィンにおける「外部性の問題」 ──『イワン・デニーソヴィッチの一日』を手がかりとして
セルゲイ・ドヴラートフの作品世界 ──『かばん』を中心にして──
K.ヴァギノフ『山羊の歌』 ──「сопоставление」の詩学──
18世紀末ロシアの喜歌劇とクニャジニーン