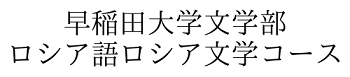2024年度
○ソローキンの作品にみられる言説の外部性について
○フィギュアスケートは芸術か否か
○ロベール・ブレッソン『ラルジャン』論
——『にせ利札』との比較および、主人公イヴォンの演出について——
○ワシリエフ『亡命の美』第 1 章「バレエ・リュスとロシアファッション」
翻訳および解説
2023年度
○シベリア鉄道の歴史と日本との関係について
○〈大泉黒石〉の誕生――黒石大泉清小伝
○日露戦争期に見る日本とロシア
○ヴェリミール・フレーブニコフ研究――「笑いの呪文」読解
○日本の現代演劇におけるスタニスラフスキー・システムの影響
○ダニイル・ハルムス研究――「遊び」と真剣さの詩と『出来事』
○思考について――レーニンを補助線として
○ウラジーミル・ナボコフとロシア文学
○ロシア、日本、東欧におけるスポーツと国民の関係性
○ロシアにおける舞台のジャポニスム
○ロシア文学のバレエ化
○イコンにおけるイメージ
○マリーナ・ツヴェターエワ『山の詩』読解――愛と記憶を中心に
○リュドミラ・ウリツカヤ作品における身体の役割――記憶とのかかわりをめぐって
2022年度
○ロシアにおけるアメリカンフットボールの受容
○タルコフスキー『ストーカー』における奇跡の確度
○ディストピア小説とその時代――『われら』『すばらしい新世界』『1984』における科学技術とその利用
○日本語母語話者のためのロシア語音声指導法
○宮沢賢治とフレーブニコフ――二人のユートピストを比較して
○ダニイル・ハルムス研究――「遊び」と真剣さの詩と『出来事』
○ロシアの採集文化――キノコとベリー
○餅とパンの日露食文化比較
○19世紀におけるロシアの音楽とナショナリズムについての考察
2021年度
○ベラルーシにおける2020年の大統領選挙とそれに対する抗議運動について
○シクロフスキー『Zoo』の解体、あるいは異化についての考察
○トルストイ『生ける屍』論
○19世紀ロシア文学における障害者形象
○チェルヌイシェフスキー『何をなすべきか』の女性たち
○ボロディンの歌曲と人生―詞に表れる19世紀後半のロシア社会とボロディンの思想―
○第二次世界大戦に従軍したソ連の女性たち―第一次、第二次世界大戦を通じた社会の中での女性の表象―
○ソ連音楽におけるVIAの展開
○マリーナ・ツヴェターエワの文学にながれる音楽―声と母に求める〈生〉―
○映画『神々のたそがれ』のリアリズム
○19世紀ロシア文学に見るロシア正教の諸側面
○アンナ・スタロビネツ「イカロス腺」翻訳および解説
2020年度
○『雪どけ』から「雪どけ」へ
○デリューシナ版『源氏物語』研究――デリューシナと紫式部の交流を見据えて
○水の境界とルサールカーーあの世とこの世を行き来するもの
○ロシア文学における「母」の変容
○ユーラシア主義と現代
○救世主ハリストス大聖堂研究――ロシアのナショナリズムをめぐって
○インノケンティー・アンネンスキー研究――「移り変わり」を捉えた詩人として
○ロシアにおける憲法体制の転換と法ニヒリズム
○ドストエフスキーにとって「神」とは何か――『罪と罰』を中心に
○ロシアのプーチン政権下における改革――ソ連末期及びロシア連邦初期との比較を通じて
○ソ連の宇宙開発に対する大衆の期待
○ロシア語の語彙学習方法考察
○ロシアにおける論理学思想の展開――命名から構成へ
○『巨匠とマルガリータ』におけるマルガリータの表象――「ソフィア」的存在として
2019年度
○『地下室の手記』と現代社会
○チェーホフ『かもめ』研究――『かもめ』に散りばめられた喜劇
○ルイレーエフ『ドゥームィ』における比喩表現の抒情的効果
○アーシャはなぜ逢い引きの場所を変えたのか―ツルゲーネフ作品に見る娘達
○チェーホフ作品の翻訳について―戯曲としての«Вишеневый сад»翻訳
○ヴィクトル・ペレ―ヴィン『iPhuck10』研究――ポスト・ヒューマン時代における恋愛と芸術
○ノルシュテイン作品における色の分析
○ドストエフスキー『貧しき人びと』研究―読むこと書くことと自意識
○レーニンと弁証法的唯物論
○ロシア魔法昔話におけるバーバ・ヤガー
○『白痴』を生きる女たち
○日ロフットボール文化比較
○パステルナーク『ドクトル・ジバゴ』研究―詩集に込められた意味
○計量テキスト分析による、ドストエフスキー『罪と罰』の分析
2018年度
○ニーチェとドストエフスキー
○日本におけるロシア料理の受容について―西洋料理から日本風洋食へ
○アンドレイ・プラトーノフ『ジャン』研究―眼差し、身体、他者―
○リュドミラ・ウリツカヤ研究
○ソヴィエト非公式芸術における初期リアノゾヴォの詩の研究
○「SF」で捉えるフョードロフの計画
○ユロージヴィ研究―『聖愚者ラヴル』を中心とした創作上での描かれ方について―
○エウゲーニー・ザミャーチンの文学理論と実践
○ロシア・アヴァンギャルドにおけるプロパガンダ芸術及びその関連文書の文体の研究―マヤコフスキイ・ヴェルトフを例に
○『地下室の手記』研究―『地下室の手記』は私小説とよべるか―
○ロシアにおける「身体」の系譜―ニコライ・フョードロフから現代にかけて
○東アジアを覆う朝鮮半島問題―朝鮮半島から波及する国際的危機の高まり
○ソヴィエトにおける革命と芸術
○ソヴィエト法思想の発展の初期段階 パシュカーニス法理論の現代的意義
○ドストエフスキー『未成年』について
○現代ロシアの記憶 / 歴史の模索―大祖国戦争の記憶 / 歴史の利用と受容
○『タバコの害について』について
○魔法昔話のモチーフ―人間の敵対者となる大蛇、協力者となる大蛇
○トルストイ『復活』についての考察―その宗教観と死生観について論じる
○日露における山・森の妖怪―山姥とレーシイを中心に
○И.А.ゴンチャローフ『オブローモフ』研究―オブローモフのメッセージ
2017年度
○ドストエフスキー『悪霊』と革命――思想、信仰と集団の必然性
○セルゲイ・ドヴラートフ『かばん』について――能『融』と比較して
○ドストエフスキー作品における個人と社会
○ロシアにおけるモチーフとしての世界樹―世界樹に込められた祈り―
○日露における妖怪とその比較
○ロシア滑稽譚に見るロシア民衆の教会観
○『魔の山』に於ける「中間」の問題とロシア文学の偏在
○セルゲイ・エセーニン抒情詩研究――エセーニン詩日本語訳を手掛かりにして
○『時計じかけのオレンジ』における“ナッドサット言葉”の翻訳
○アファナーシィ・アファナーシエヴィチ・フェート『Вечерние огни』翻訳
○『馬鹿たちの学校』におけるレトリックの分析
○ドストエフスキーの登場人物について
○北方諸民族の食と伝承――生活と信仰との関係性
2016年度
○ガルシン作品研究――読み消されたテクスチュアリティ
○ロシア近代文学にみられる「アジア」――フレーブニコフの詩作とユーラシア主義におけるアジア観の比較
○ヨシフ・ブロツキイ『ゴルブノフとゴルチャコフ』考察――「会話」による時間脱却の試み
○マクシム・ゴーリキイ研究――ゴリキイの初期作品からみる『どん底』
○戦争と音楽――ソヴィエトの巨匠と交響曲
○ザミャーチン『われら』について
○『タレルキンの死』におけるグロテスク性の研究
○オシップ・マンデリシュターム『石』読解――歴史観にみる建築と永遠性
○ロシア・シオニズム研究――なぜ「ビロビジャン計画」は頓挫したのか
○ドストエフスキー『おとなしい女』とアンドレ・ジイド『狭き門』
○ベールイ『ペテルブルグ』について
○「余計者」について
2015年度
○ゴーゴリ演劇のアクチュアリティ――『査察官』だんまりの場をめぐって
○アゼルバイジャンにおける若年層の飲酒習慣と宗教意識
○ロシア連邦内におけるブリヤート――結婚、言語から
○ロシア人は第二次世界大戦をどう受け止めたか――「大祖国戦争」と「戦勝記念」から考える
○アンドレイ・ベールイ『シンフォーニヤ』翻訳と付論
○外国人向けロシア語教育
○チェーホフと平田オリザ――アンドロイド版『三人姉妹』を通して
○ドストエフスキー『白痴』研究――「本当に美しい」人間像
○ソ連時代の食文化研究
○現代におけるコサックとロシア
○ハルムスの作品における「作者」と「読者」の関係
○レオニード・アンドレーエフ論――ナロード・テロリズム・都市
○ユーリイ・オレーシャ『羨望』における価値観の闘争――「言語的多様性」を暴露する想像力
○ブルガーコフ『犬の心臓』論
○ヴィクトリヤ・トーカレワ『嘘のない一日』翻訳
○ロシアにおける俳句の受容
○マクシム・バグダノーヴィチ研究――ベラルーシ性の探求
○ガガーリンのヒーロー性――ソ連栄光の象徴から普遍的な象徴へ
○『悪霊』キリーロフの思想――もはやヒトではいられない
○レールモントフ『現代の英雄』研究――ペチョーリンの演劇性と運命論について
○ロシアのフィギュアスケート――伝統文化の流れ
○モスクワの地下鉄――「宮殿」としてのメトロ
○演劇性にみる映像の可能性――A.タルコフスキー『サクリファイス』論
2014年度
○スターリンの自民族意識
○露宇関係の変遷と、移民にみるウクライナ情勢
○チンギス・アイトマートフ「富士登山」の翻訳と考察
○日本現代文学におけるドストエフスキーの受容―中村文則の作品から―
○19世紀「コーカサス作品」におけるコサックの役割
○チェコのアニメーション―その歴史と位置づけ―
○トルストイ『コーカサスの捕虜』論
○19世紀のロシア帝国の中央アジア進出―クルグズ人を中心に―
○一神教と逸脱
○ロシア神秘思想とフランク・ロイド・ライト
○英露比較でみるロシア語の語順類型
○アンドレイ・プラトーノフの描く人間と世界―「ジャン」とはなにか―
○SF文学と世界―日本におけるソビエトSFの受容を中心にして―
○アレクサンドル・ソクーロフの作品における空間表現について―ペテルブルグという都市空間
○ロシアにおける陰謀論
○ザミャーチン『われら』研究
○日露エネルギー事情の現状分析とその展望―シェール革命に沸く世界で日露が生き残る道とは―
○『現代の英雄』論―自己演出と自己劇化―
○ジナイーダ・ギッピウスの内的世界
○Григорий Остер «Дети и эти» 翻訳
2013年度
○ロシアにおける同性愛
○バリモント翻訳
○セルゲイ・ドヴラートフ『ゾーン 看守の手記』の翻訳
○チェーホフの死生観について―死を眺めるチェーホフ―
○サーシャ・ソコロフ『犬と狼のはざまで』の考察
○ヴィクトル・ペレービン『恐怖の兜』について
○「サルタン王物語」におけるビリービンの挿絵についての考察
○トルストイ『コーカサスの捕虜』論
○チェーホフ『かもめ』研究―舞台上の「家」と死んだ「かもめ」―
○A.N.オストロフスキー『罪なき罪びと』翻訳
○ソヴィエト連邦の民族問題―グルジア・アブハジア問題によせて―
○ゴロヴニン事件
○アルセーニー・タルコフスキー研究―孤高の詩学―
○ロシアにおける日本サブカルチャー~日本アニメから見るモスクワ若者文化~
○現代ロシア文学における女性のジェンダー/セクシュアリティ―女性作家の作品世界から―
○アレクサンドル・ボロディン
○ミハイル・クズミン『翼』翻訳
○プラトーノフの幸福観―「ジャン」・「帰還」から―
○ヴィクトル・ペレ―ヴィン『オモン・ラー』考――プロットから見るその主題――
○ロスラヴェッツのピアノ独奏曲分析―『ピアノソナタ第1番』と『ピアノソナタ第5番』の比較―
○戦間期のイヴァシュキェヴィッチの散文について
○クルガーノフ『18世紀末―19世紀初頭のロシアの文学的アネクドート』翻訳―エカテリーナの栄光ある時代―
○ミハイル・ショーロホフ著「静かなドン」に描かれる個人の幸福
2012年度
○ロシアとフリーメイソン
○テクストとイメージのモンタージュ―集団行為「郊外への旅」研究―
○ロシア文学における多民族表象について―異文化コミュニケーションと他者―
○ゴーゴリ作品の和訳について―「鼻」と「外套」における語りの翻訳―
○タチヤーナ・トルスタヤ『ぺテルス』論―主人公の〈胎児性〉と物語の時空間―
○ロシア正教―教会建築と聖愚者にみる異常性―
○レールモントフの叙事詩「デーモン」について―改稿過程から8稿の意義を考える―
○『罪と罰』研究―ソーニャの愛―
○萩原恭次郎とマヤコフスキー―その類似性:語彙、形式、社会的状況からみる「アヴァンギャルド」と「政治思想」
○ロシアにおける短歌の需要
2011年度
○ロシアの最新ヒットソングの翻訳とその考察
○ロシア・アニメーションと日本アニメ
○ロシア語学習者のためのセルビア語講座
○ザミャーチン『われら』論―I-330と「個」の意識を目覚めさせる力-
○ゲルツェンのノヴゴロド観―スラヴ派と西欧派の狭間で―
○国民音楽家チャイコフスキーの誕生
○アクーニン『かもめ』の翻訳
○ゴンチャロフ『オブローモフ』について
○『白痴』について
○オセチアの「ナルト叙事詩のシュルドン」から見るトリックスター
○ヴィソーツキー詩集『Нерв』の翻訳
2010年度
○ラスプーチン考 ~『マチョーラとの別れ』における老人
○プラトン・カラターエフ論 ―レフ・トルストイから見た「民衆」の形象―
○アンナ・アフマートワ
○M・A・クズミーン 翻訳と研究
○ソログープ『夜ごとの踊り』について -「美」が守られる世界―
○スタニスラフスキイ・システムとわたし
○ザミャーチン『われら』研究 ―ファム・ファタールとはなにものか?―
○イワン・ブーニン ―その死生観をめぐって―
○ロシア的なものとは何か ~日露文化交流の将来像を探る~
○ロシア語口語訳聖書の書誌的研究とそのコンコーダンス作成
○エフレーモフ研究 ~『アンドロメダ星雲』における協調~
2009年度
○ナールビコワ研究 ―ペレストロイカが文学に与えた影響―
○『巨匠とマルガリータ』研究 ―悪魔たちのルーツ―
○聖像画とパーヴェル・フロレンスキイ
○アファナーシエフ『ロシア民話集』から見る食文化
○『戦争と平和』について ―トルストイに見るロシアの生命の営み―
○近現代ロシア文学翻訳論 ―ツルゲーネフ『Свидание』の翻訳の考察から―
○プーシキン『モーツァルトとサリエーリ』について ―或る天才と天に意義を申し立てた男の悲劇―
○ツルゲーネフに見る19世紀ロシアの女性像
○ガルシン論 ~「善」について~
○読者の身体と作者の目 ―ウラジーミル・ナボコフの『ディフェンス』を巡って―
○ゴンチャローフ作品における「余計者」像の変遷
○エイゼンシテイン研究 ―「戦艦ポチョムキン」をどのように見るか―
○Тетрис考
○『復活』に反映するトルストイの道徳観と芸術観
○ショスタコーヴィチ研究 ~抵抗と魂の音楽~
○ウクライナ化と民族・言語の諸問題
○ロシアの虚無主義
○チンギス・アイトマートフの『一世紀より長い一日』と『チンギス・ハンの白い雲』について
2008年度
○アフマートワ
○リシツキーとブックデザイン
○『アンナ・カレーニナ』について-恋愛・結婚・家庭-
○発展は悪か
○ダニイル・ハルムスの哲学的散文の翻訳
○ザミャーチン「われら」についての考察~「毛むくじゃらの私」とネオリアリズム
○ゴーゴリの『鼻』について
○『ドクトル・ジバゴ』考察
○芸術家アンドレイ・タルコフスキーとその観客
○ミハイル・ヴルーベリ論
○犬を連れた奥さんについて
○ロシアSFにおける宇宙開発
○アレクサンドル・グリーン-森のできごと、他四篇-
○日露の言文一致運動~偶然と必然の狭間~
○ドストエフスキー論
○ハルビンとロシア人
2007年度
○亡命ロシア文学とマイノリティ研究
○トルストイの文学におけるエゴイズム考える
○他民族的都市プラハの最盛期とチェコ人の行動方針について
○武道とバレエ――日本とロシアの身体観――
○英雄の思想――ロシア文学から現代日本のサブカルチャーまで――
○ヘンルィク・シェミラツキ研究――19世紀ポーランド人画家の生涯と作品――
○ブルガーコフの初期短篇をめぐる試論
○リアリティーの在り方――チェーホフとイプセン――
2006年度
○エゴイズム考
○ロシアの民話について
○ドストエフスキー『地下室の手記』について
○ユーリ・ノルシュテイン――『話の話』について――
○ドストエフスキーの語り――『地下室の手記』考察――
○ユーゴスラビア――歴史とナショナリズム――
○鳥と他界観
○バーバ・ヤガーと山姥の比較
○イデオロギー装置としてのロシア語詩について――マンデリシタームとマヤコフスキー、その実作と社会との接触点を考える――
○ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』における演劇的虚構性について
○ロシア映画大学での俳優教育術
○ヴィデオアートの根源をヴェルトフに探る
○フレーブニコフ『ザンゲジ』論
○ブルーノ・シュルツの世界――隘路と抜け道のはざま――
○カシヤーン・ゴレイゾフスキーの実験的バレエ――『美しきヨセフ』を中心とした考察――
○カンディンスキーにとっての空間――内なる真空――
○現代日本の「オブローモフ主義者」たち
2005年度
○ソ連時代の出版と少数民族
○プロコフィエフ
○ロシアにおける魔法民話について
○スラヴの民族宗教研究
○ロシアの民族舞踏アンサンブル モイヤーエフバレエ団
○チェーホフの墓
○ミラン・クンデラ『冗談』 ノスタルジア表象空間
○イリヤ・カバコフと現代
○『動くな、死ね、甦れ』と少年の視線
○マニフェスト「芸術を生活の中へ」
○日本におけるドストエフスキーの受容――「罪と罰」受容のいきさつとドストエフスキー体験及びその影響と深さ――
○ドストエフスキー・その小説――「罪と罰」に於けるバフチン理論の考察――
○現代ロシアにおける社会問題
○フリャーギンとは誰か
○ブルガーコフ試論――飛翔する力と光の世界――
○ペトルシェフスカヤの短編をめぐって
○大黒屋光太夫の実像――真の光太夫像に迫る――
○ブリューソフ小説の翻訳
○ユーリー・ノルンシュテイン――アニメーション監督という芸術家――
○『悪霊』論――語りの視点の諸問題――
○ロシアの絵本
○プーチンとメディア
2004年度
○チェーホフ――ユーモアの視点――
○エルミタージュ――華麗なる美の殿堂――
○ロシア思想における観念の臨海をめぐって
○ブルガ-コフ論
○ヴェルトフ以降――芸術による世界の再配置について――
○ロシアの詩について――ロシアにおける「詩」の位置づけ――
○ロシアにおける日本美術の流入
○ロシアのイコン
○エカチェリーナ――その人生とリーダー性――
○決闘――プーシキン――
○くるくるぺてるぶるく――ベールイ『ペテルブルクの表面性』――
○ツルゲーネフ論――その生涯と作品、ヒロインの魅力をめぐって――
○スラヴ民話の世界観――モチーフから語られる風景へ――
○オデッサ――バーベリを通した記号論的解明――
○フィギュアスケート界におけるロシア――その影を落とした日本のマンガと、そしてロシアの現状と――
○近代ロシアと民衆芸術――ロシア民衆芸術の再発見――
○周縁から見たロシア――観察者カバコフ――
○ロシアのポスター芸術――ロシア・アヴァンギャルドを中心に――
○巨匠とマルガリータにおける悪魔論――神性と魔性――
○ロシア民話
○チェーホフ原作による映画「機械じかけのピアノのための未完成の戯曲」の考察
○ビオメハニカ
○異化と芸術――ビオメハニカの再解釈から求める異化の現代的有効性――
○ロマニ語の言語学的考察――ロマ民族の歴史と文化から――
○ロシア文学とレイモンド・カーヴァー
2003年度
○ボリス・サヴィンコフ論
○ロマン・ヤコブソンと構造主義
○ソ連崩壊とロシアスポーツ――ロシア・サッカー代表の弱体化
○モスクワの都市像――『巨匠とマルガリータ』を通して見るモスクワ
○絵画から写真へ――A. ロトチェンコの研究
○ロシアと競馬
○カラムジンとセンチメンタリズム
○ベルジャーエフの思想における「主体お客体」――夢の丘にて
○バレエ『春の祭典』とニーチェ思想
○アンドレイ・タルコフスーの『鏡』について――世界へ回帰する記憶
○ブルガーコフ『至福』翻訳
○アレクサンドル・ソクーロフ論
○ロシア正教における霊性(スピリチュアリティ)の考察
○お金をめぐるドストエフスキー小説
○チェーホフと20世紀演劇
○バレエ・リュス論――フォーキン、ニジンスキーの時代
○ロシア映画における宗教性についての考察
○『罪と罰』論――水と油
○ロシア・ウクライナ・ローマ――ゴーゴリが辿った3つの軌跡について
○ゴーゴリ論――「ペテルブルグもの」の世界
2002年度
○歓喜の画家ヴァレンチンセローフ
○『カラマーゾフの兄弟』と聖書
○旧ソ連のアルヒーフ公開制度
○不滅のマヤコフスキー
○『バロン・ウンゲルン-ウルガとアルタンボラク』翻訳
○イマージュ、そのとらわれしもの
○タタール人について
○革命のトラウマと詩人マヤコフスキーの声
○プーシキン作品におけるペシミズム
○スクリャービンと西欧文化
○マレーヴィチ論
○20世紀ロシア演劇の冒険者たち
○「イワン・デニーソヴィチの一日」出版の政治的・歴史的背景について
○亡命者の文学
○コミック・シーンにおける日露比較研究
○ドストエフスキーにとって救済とは何か
○シクロフスキーと荒川修作
○ロシア映画監督3人に見る個性と現代
○ソビエト・ロシアのジャーナリズムについて
○ロシア・市場経済への変遷
○チェーホフ世界の深化の過程
2001年度
○アファナーシイ・ニキーチン『三つの海の彼方への旅』の翻訳
○ロシア文学における悪女論
○「ミステリヤ・ブッフ」におけるメイエルホリド演出
○日本におけるゴーゴリ
○ジュコーフスキイ論
○トルストイの『イワン・イリイチの死』の研究
○プーシキンの『エヴゲーニィ・オネーギン』研究
○『ノスタルジア』のタルコフスキー
○アレクサンドル・ブローク『イタリア詩篇』研究
○表現方法における日露の比較検討
○ロシアと国際社会
○ドストエフスキイと現代の社会問題
○ロシアの児童文学
○ロシア現代SF小説の翻訳
○『カラマーゾフの兄弟』における西洋悲劇精神について
○プロパガンダ
○アンドレイ・プラトーノフ「ジャン」について
○「力強き仲間」
○ミハイル・ブルガーコフ
○マレーヴィチにおけるセザンヌ主義とシュプレマティズム
2000年度
◯ロシアのラグビー
◯革命期ロシアでさかんに行われた外国語の使用
◯チェーホフ──三つの作品に寄せて──
◯ガルシン──その生涯と作品──
◯パステルナーク論──詩の初期から探る創作の特徴──
◯ロシアとドイツの魔女について──アファナ-シエフ民話集とグリム童話──
◯クルィロフ研究──『魚の踊り』と検閲問題──
◯ゴーリキー作品が日本の文壇に与えた影響
◯バフチン論──カーニバルの要請──
◯アヴァンギャルド演劇──『南京虫』におけるマヤコフスキイとメイエルホリドの試み──
◯ウラジーミル・ヴィソツキイ──俳優として、詩人として──
◯ヴィクトル・ペレーヴィン──『虫の生活』を中心に──
◯イサーク・バーベリ研究──『騎兵隊』を中心に──
◯ソクーロフの作品におけるチェーホフ像
◯スターリン体制と群集心理
◯ロシアSF文化論──SFという枠組みとザミャーチン、ストルガツキー──
◯ロシアという名のボロフスコイミール
◯ミハイル・プリーシヴィンについて
◯ゴーリキーとソビエト作家同盟
◯И.А.Бунинについてのエチュード