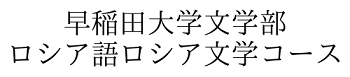「ロシア語ロシア文学コース」は早稲田大学における戦前からのロシア語・ロシア文化研究の伝統を受け継ぎ、その最前線を牽引するユニークなコースである。
ロシアは帝政時代から革命、ソビエト連邦時代、そしてソ連崩壊後の現在と、激しい歴史の転変を潜り抜け、それに伴いロシア文学とロシア文化も、めまぐるしく変貌を繰り返してきた。しかし民謡・民話などのフォークロア、『イーゴリ軍記』に代表される中世文学、プーシキン、ゴーゴリ、トゥルゲーネフ、ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフ、パステルナーク、ソルジェニーツィンといった巨匠たちの芸術は、時代を超えて生き続け、その輝きを今も失わない。そのロシアはまた私たちに最も近いヨーロッパとして日本と深い関わりを持ち続けてきた。
そのロシア文学・文化研究の伝統を振り返るなら、ロシア正教、マルクス主義、ソビエト構造主義といった様々なイデオロギーや方法が分析のために用いられてきた。しかしそれらの多様な視点も大きな脱中心化の波に洗われており、ロシアは私たちの目の前に全く新しい姿を現そうとしている。
「ロシア語・ロシア文化コース」はロシア語学の習得と伝統的なロシア文学の知識を踏まえながらも、このような状況に対応しつつ新しいロシア文化・文学像の獲得に努めてゆく。
◆早大露文の歩み
1920年(大正9年)、早稲田大学文学部にロシア文学専修が設置された。1937年(昭和12年)に戦時のため一時閉鎖されたが、戦後の1946年 (昭和21年)に復活、2002年ロシア語・ロシア文化専修に改称・改組される。
このような古い伝統を受け継ぐ露文専修は、しかし今や単に日本におけるロシア文学・文化研究の中心的な場であるにとどまらない。ペレストロイカからソヴィエト連邦崩壊を経て10年が経過した現在、ロシア文学・文化は様々なジャンルにおいて劇的な変貌をとげようとしている。古い「ロシア」の固定観念の背後に隠されていた旧ソ連の民族文化はその多様性をアジアとヨーロッパの双方に豊かに現しつつある。それはスラヴ・東欧と北方ユーラシアに広がる最も豊かな文化的可能性を秘めた地域のひとつなのである。
現在の露文専修は、このような状況に対応しつつ、中世から現代にいたるロシア文化の流れを軸に、しかし古い「ロシア」の概念にとらわれることなく、新しい「ロシア文化」、さらにはスラヴ・東欧文化をとらえ直していこうとしている。
◆教育方針と教科内容
ロシア語・ロシア文化専修で学ぶためには、ロシア語の修得が課題となるが、これは他のスラヴ語を学ぶための手掛かりや、旧ソ連の民族文化に触れる窓口ともなるものである。このロシア語の読み・書き・話す力を1年次から養い、ロシア語の言語としての特質にも触れつつ、専門科目では原典による文学および文学評論の講読のみならず、演劇・映画・音楽・思想といったロシア文化の多様なジャンルに原語で触れていく。また、選択演習は複年履修が可能なので、ロシア文化の興味のある分野を重点的に、より深く学ぶことができる。
◆卒業生の進路
語学をはじめ専修で学んだことを生かして、テレビ・新聞・雑誌などの記者やディレクター職に、三井や三菱などの総合商社で石油資源開発や機械輸出の対露エキスパートとして、さらには旅行業界などで活躍している卒業生が多い。あるいは広告代理店やメーカーへの就職、特にここ数年では情報産業分野への就職も増加しており、ロシアにとらわれない幅広い分野へも進出している。また、留学や大学院への進学も増加傾向にある。
具体的に過去の就職状況だけを顧みても、モスクワ放送、電通、フジテレビジョン、TBS、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、通信社のラヂオプレスなどマスコミ各社に、さらにはワールド航空サービスなどの旅行代理店、コンピューターシステム開発のオービックシステムエンジニアリング、東芝、NTTドコモなどに人材を輩出している。
留学に関しては、モスクワ大学、ウラジオストクのロシア極東国立総合大学などへの一年間の長期交換留学のほか、ロシア極東国立総合大学への夏季短期留学プログラムが準備されており、私費留学や院生も合わせると毎年コンスタントに10人前後の露文生がロシアで学んでいる。
■2025年度コース在籍学生数
|
学年
|
人数(名) |
|
2年
|
8 |
|
3年
|
8 |
|
4年以上
|
17 |
| 計 | 33 |
早稲田大学文学学術院 露文コース室
e-mail: [email protected]
tel: 03-5286-3740